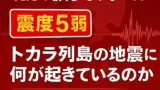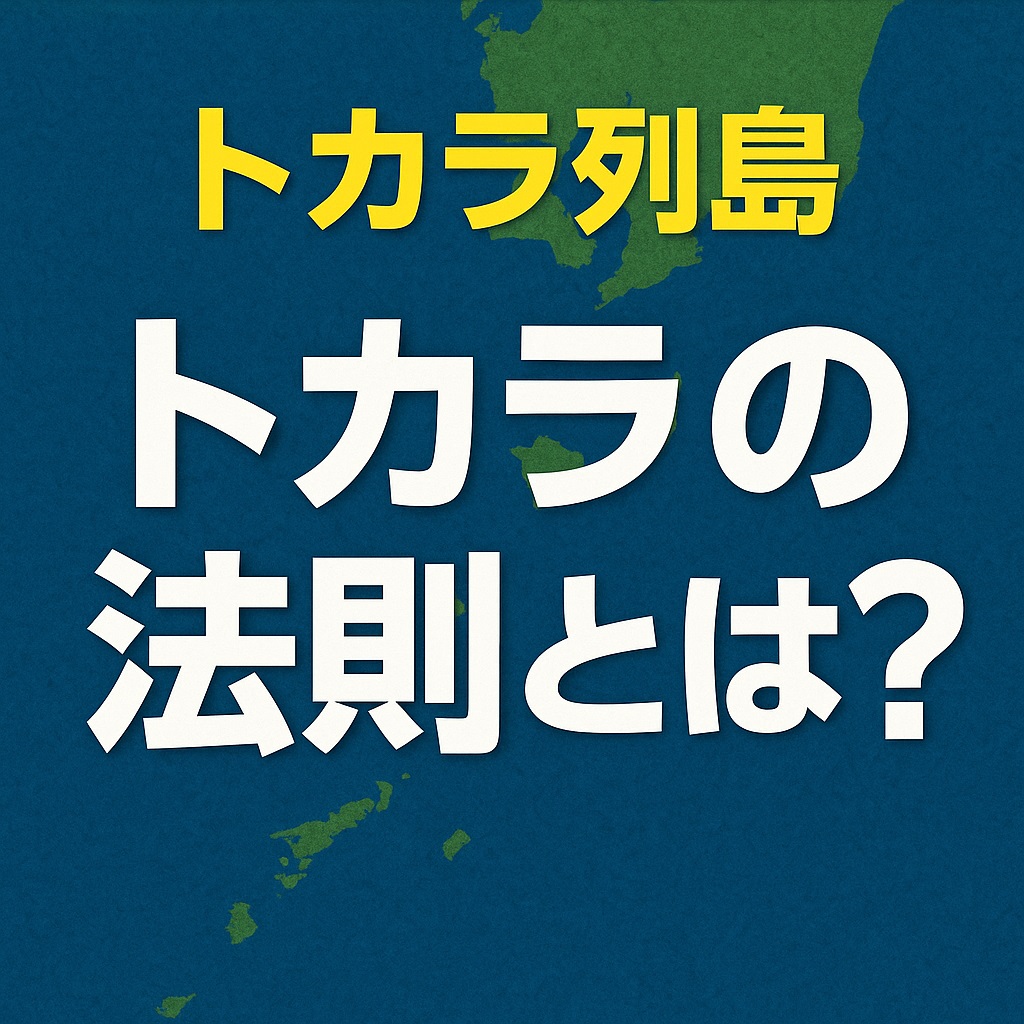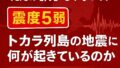最近SNSやニュースで耳にすることが増えた「トカラの法則」。
これは、鹿児島県のトカラ列島で群発地震が起こると、その後日本国内のどこかで大きな地震が起きる――という“法則”のようなものです。
一見するとオカルトや都市伝説のようにも聞こえますが、果たしてこの「トカラの法則」はどれほど信憑性があるのでしょうか?
本記事では、「トカラの法則」の概要と、実際に“当てはまった”とされる過去の事例について紹介します。
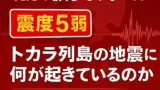


「トカラの法則」とは?
「トカラの法則」とは、鹿児島県のトカラ列島で群発地震が発生すると、その後1〜2週間以内に日本列島の他地域で大きな地震(震度5弱以上)が起きるという経験則のようなものです。
この名称は、正式な学術用語ではなく、SNSや一部の地震観測者の間で使われ始めた俗称に過ぎません。
ただし、過去の事例の中に「トカラ列島で群発地震 → 国内で大地震」という流れが一定の頻度で起きていたことから、都市伝説的な広がりを見せています。
科学的な根拠が明確に示されていないにもかかわらず、多くの人がこの“法則”に注目しているのは、「経験的なパターン」が存在するように見えるからです。
あくまで「俗説」であり、科学的根拠はない
まず前提として重要なのは、「トカラの法則」は地震学的に確立された理論ではないということです。
地震を予測するためには、厳密な物理モデルや地殻構造、プレートの動きに関する科学的データが必要です。
しかし「トカラの法則」にはそうした裏付けがなく、過去にたまたま一致した例がいくつかあるに過ぎません。
気象庁をはじめとする研究機関も、この法則に関する公式見解や支持は出していません。
したがって、「トカラの法則に当てはまったから次に大地震が起きる」と断定するのは、科学的に無責任な解釈と言えます。
ただし、過去の観測データを注意深く見ることで、防災意識を高める契機になるのであれば、完全に無意味とも言い切れない側面もあります。
なぜ信じられやすいのか?心理的要因を解説
「トカラの法則」が広く信じられている理由の一つは、「後付けでも因果関係があるように感じてしまう」人間の心理傾向にあります。
例えば、2021年12月のトカラ列島の群発地震のあと、山梨県や和歌山県で震度5弱の地震が発生しました。
このような事例があると、まるで「やはりトカラ列島の揺れが前兆だったかのように」錯覚しがちです。
これは“後知恵バイアス”と呼ばれる心理現象で、出来事が起きた後にその原因を過剰に結びつけてしまう傾向があります。
一部のYouTubeチャンネルやSNS投稿が不安を煽るような内容で拡散することで、信じる人が増えていく構図になっています。
情報の信頼性や出典を確認せずに受け入れてしまうことは、防災意識の混乱にもつながりかねません。
防災上のメリットも?注意すべき“正しい受け止め方”
「トカラの法則」そのものに科学的な正当性がないとはいえ、それが防災意識を高める“きっかけ”になるのであれば、それなりの意味はあるかもしれません。
たとえば、「トカラ列島で地震が多いときは、全国的にも揺れに注意しておこう」と考えることで、日頃の備えを見直す人が増えるなら、それはポジティブな効果とも言えます。
重要なのは、単なる予言や噂としてではなく、一つの“観測データの傾向”として冷静に受け止めることです。
不確かな情報に踊らされず、気象庁などの公式発表やハザードマップ、防災指針に基づいて行動することが基本です。
また、トカラ列島の群発地震は火山活動とも関係がある可能性があるため、地震だけでなく火山情報にも目を向けるとよいでしょう。
「トカラの法則」的中率の検証は難しい
もう一つ問題になるのが、「この法則がどれだけ当てはまっているのか」を検証するのが非常に難しいという点です。
地震は毎年のように日本各地で発生しており、トカラ列島でも一定の頻度で群発地震が起きています。
仮にトカラの群発地震の後に他の地域で揺れたとしても、それが「法則通り」と言えるのか、偶然にすぎないのかを明確に判断する手段は限られています。
また、地震の発生地域や規模に明確な関連性が見られない場合も多く、地震発生のメカニズムそのものが非常に複雑であることから、単純な“法則化”には慎重になる必要があります。
信じる・信じないではなく、「正しく付き合う」という姿勢が求められますね。
- https://www.asahi.com/articles/ASQDG6TLQQD8TLVB00R.html
- https://weathernews.jp/s/topics/202112/090145/
- https://news.yahoo.co.jp/articles/42c78c709dc059086e585426d5cbf7a0585fd144
過去に「トカラの法則」に当てはまったとされる主な事例
「トカラの法則」とは、トカラ列島で群発地震が発生した後に、国内の別地域で中規模以上の地震が発生する傾向があるという経験則です。
科学的に確立された理論ではありませんが、過去の地震の発生タイミングを見ると、この法則に「当てはまった」とされるケースがいくつかあります。
この章では、具体的な発生日と震源地、規模、そして注目された理由をもとに、代表的な事例を詳しく解説します。
どの程度この法則に信憑性があるのかを考えるうえで、まずは事実ベースの振り返りが重要です。
2021年12月:トカラ列島群発地震とその後の連鎖的地震
2021年12月2日から10日にかけて、トカラ列島近海で700回を超える群発地震が発生しました。
この期間中、口之島周辺で最大震度4の揺れが何度も記録され、島民の生活にも大きな影響が出ました。
その直後、12月9日には山梨県東部・富士五湖付近で震度5弱の地震、同日夕方には和歌山県北部でも震度5弱の地震が発生しました。
これらの連鎖的な発生により、「トカラの法則がまた当たった」とSNSや地震ファンの間で一気に話題となりました。
ただし、気象庁はこれらの地震の因果関係について否定も肯定もしておらず、偶然の可能性も残されています。
2011年1月〜3月:トカラ列島の群発と東日本大震災
2011年1月、トカラ列島でやや強めの群発地震が発生しました。
そのわずか2か月後の3月11日には、皆さんご存じの東日本大震災(M9.0)が発生しています。
この2つの地震が時間的に近接していたことから、後年になって「前兆だったのでは?」とする意見が一部で見られるようになりました。
しかし、当時の専門家は直接的な因果関係については明言しておらず、広域的なプレート運動の活性期にあったという認識にとどまっています。
地震の因果関係を語る際には、時間的な近さだけでなく、プレート構造・震源の深さ・断層活動などを精査する必要があるという点にも注意が必要ですね。
2024年12月〜2025年1月:能登半島地震との関連性?
2024年12月下旬、トカラ列島で小規模な地震が数日間続けて観測されていました。
そして年明けの2025年1月1日、石川県能登半島でM7.6の大地震が発生。
このタイミングの近さから、「またトカラの法則が当たった」とSNSで再燃しました。
ただし、この事例も地理的距離やプレート構造が大きく異なるため、専門家からは「直接的な関係は不明」とされています。
同時期にプレートの活動が活発化していた可能性はあるものの、あくまで“結果論”として扱われています。
事例をまとめた一覧表
| トカラ群発地震の時期 | その後の地震 | 規模・震度 | 因果関係 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月2日〜 | 12月9日:山梨・和歌山 | いずれも震度5弱 | 因果関係は不明(偶然説も) |
| 2011年1月頃 | 3月11日:東日本大震災 | M9.0・最大震度7 | 時間的近接のみ/関連性は不明 |
| 2024年12月頃 | 2025年1月1日:能登半島 | M7.6・最大震度7 | 関連性は否定されている |
このように、「トカラの法則」が当てはまったとされる事例はいくつか存在します。
しかし、それぞれのケースにおいて科学的な因果関係が立証されたわけではありません。
地震はあくまでプレートの歪みや断層の滑りによって発生するものであり、複数の要因が絡む現象です。
「当てはまった」という感覚や印象と、科学的な関連性は分けて考える必要がありますね。
—
参考記事
- https://news.yahoo.co.jp/articles/fc5e61ff64ae37f3b1db92e33e8393c589507ec4
- https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211209/k10013382001000.html
- https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE091G30Z01C21A2000000/
新着記事
こちらの記事もおすすめです。
「トカラの法則」に科学的根拠はあるの?
「トカラの法則」は一部のインターネットユーザーの間で話題になっている現象ですが、気になるのはその信憑性や科学的な裏付けですよね。
トカラ列島の群発地震が発生した後に他地域で大きな地震が続いたという過去の例から、「何かの前兆では?」と考える人が増えた一方、科学的な立場ではどう捉えられているのでしょうか。
ここでは、「トカラの法則」が実際に地震予知に使えるものなのか、また専門家がどのように見ているのかを詳しく掘り下げていきます。
学術的には「法則」とは認められていない
まず大前提として、「トカラの法則」は正式な学術用語ではなく、気象庁や地震研究機関による命名でもありません。
そのため、科学的に体系づけられた地震予知理論として確立されているものではないのが現状です。
気象庁も公式に、「トカラ列島での群発地震と他地域の地震との因果関係は不明」としています。
一部の研究者によっても、相関が“あるように見える”ことがあっても、それが統計的に有意かどうかは証明されていません。
「たまたま重なった」可能性も否定できない
日本はプレート境界に位置する地震多発国であり、全国で毎日のように地震が発生しています。
そのため、どこかで群発地震が起きている最中に、他の場所でも中〜大規模な地震が起きる確率はもともと高いのです。
「トカラで揺れたから別の地域も揺れる」という見方は、後付けの印象効果(バイアス)に過ぎない可能性が高いとされています。
気象庁や研究機関は、このような地震の連鎖を「科学的な予知」としては扱っておらず、あくまで偶発的な一致と捉える傾向が強いです。
一部の研究者は「地殻活動の活性化」として注視
一方で、すべてを「偶然」と切り捨てるのではなく、「地殻活動が広域的に活発化している可能性がある」と見る専門家もいます。
トカラ列島はユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界に近く、マグマ活動やプレートのひずみに敏感な地域です。
このような活発な地域での群発地震は、地下深部でのストレス変化や流体移動といった「エネルギーのやりとり」の一端を反映していると考えられています。
その影響が、近隣または離れた断層に伝わりやすくなっている可能性は否定できません。
ただし、これはあくまで仮説段階であり、予知につながる明確なロジックは今のところ存在していません。
「トカラの法則」をどう扱えばいいのか?
現時点では、「トカラの法則」は地震の予知や警戒基準として用いるべきものではありません。
しかし、地震に対する意識を高めるきっかけとして受け止めることには意味があると考えられます。
実際、2021年12月のようにトカラの群発地震の直後に他地域でも地震が起こるケースが何度か見られたのは事実です。
このような動きを「きっかけ」に、防災意識を再確認したり、備蓄や避難経路の確認を行うことは非常に有効です。
「科学的ではない=無意味」ではなく、正しく理解して活かす姿勢が大切ですね。
まとめ:科学的根拠は薄いが、意識を高める“サイン”にはなり得る
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 正式な学術用語ではない | 「トカラの法則」はネット上で使われる俗称です |
| 科学的根拠は未確立 | 因果関係を示す明確な証拠は確認されていません |
| 偶然の一致の可能性あり | 日本は地震が多いため、時期が重なることは珍しくありません |
| 一部研究者は広域的な活性化と解釈 | 地殻活動全体が動いている“兆し”と見る立場もあります |
| 防災意識のトリガーとして有効 | 「予知」としてでなく「備えるきっかけ」として捉えるのが◎ |
「トカラの法則」を盲信するのではなく、冷静に捉えたうえで、日々の備えに役立てていきましょう。
参考記事
- https://weathernews.jp/s/topics/202112/130125/
- https://www.jma.go.jp/jma/press/2212/13a/20221213_tokara.html
- https://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/3/2/32817.html

「トカラの法則」をどう受け止めればいいのか?
「トカラの法則」は、トカラ列島で群発地震が起きると日本の別の地域で大地震が発生する――という経験則的な“法則”です。
SNSやネット掲示板を中心にたびたび取り上げられますが、科学的な根拠は明確に示されておらず、研究者の間でも意見が分かれるところです。
それでも一般の人々がこの法則に敏感になるのは、過去にいくつかの出来事が「偶然とは言い切れないタイミング」で起こったという事実があるからです。
このような現象に対して、私たちはどう向き合えばよいのでしょうか。
「科学的根拠がないから無視」は正しい姿勢か?
結論から言えば、科学的に根拠がないという理由だけで完全に無視するのは、慎重さを欠く判断になりかねません。
現代の地震学でも、「いつ・どこで・どれだけの規模の地震が起きるか」を正確に予測することはできていません。
トカラ列島のような活発な地震・火山活動地帯での異常な群発地震は、地殻のどこかで広域的な応力変化が起きているサインである可能性も考えられます。
あくまで“可能性”の話であり、確定的な因果関係は証明されていない点には注意が必要です。
それでも、異変の兆候に敏感であること自体は、防災の観点からは決して悪いことではありませんよね。
「不安を煽る」と「備える」は別の話
「トカラの法則」を話題にすると、「不安を煽っている」と受け取る人もいます。
しかし、重要なのはその情報をどう活用するかです。
あくまで「こういう傾向があるらしい」という参考情報として捉え、自宅の耐震対策を見直すきっかけにするなど、防災行動に結びつけることが大切です。
事実、過去の大きな災害でも「まさかこんな時に…」という油断が被害を拡大させたケースは少なくありません。
「法則を信じる・信じない」にこだわるよりも、「それを聞いた今、何ができるか」を意識するほうが建設的です。
“不安を煽られる”のではなく、“今できる備えを考える”ための材料として受け止めるのが良いと思いますよ。
過去データから学び、「予兆」を生活に活かす
「トカラの法則」が注目される理由のひとつに、過去にそのような「前触れ」のような事象が実際にあったことが挙げられます。
ただし、これらは因果関係というよりも、タイミングの重なりによって人々の印象に残っている可能性も否定できません。
しかし、防災の原則のひとつに「想定外を想定する」という考え方があります。
たとえ確実性がない予兆であっても、それを契機に備えることができるのであれば、十分に意味のある行動と言えるのではないでしょうか。
近年では、スマホアプリやSNSでもリアルタイムで地震情報が手に入るようになっています。
「情報を不安の種にするか、安心の材料に変えるか」は、私たち次第とも言えますね。
「法則」は万能ではない。でもきっかけにはなる
繰り返しになりますが、「トカラの法則」に確実な予知機能はありません。
それでも、地震の可能性に対する意識を高めるという点においては、大いに意味があります。
天気予報と同じで、「降るかもしれない」と思えば傘を持っていくように、「揺れるかも」と感じたときに備えておくことは、決して無駄ではありませんよね。
「外れるかもしれない」からといって何も備えないのは、リスクマネジメントとして本末転倒です。
大切なのは、根拠が不十分な“法則”にすがることではなく、それを通じて自分の行動を変える力を持つことです。
その意味で、「トカラの法則」を完全に否定せず、柔軟に受け止める姿勢が、今の時代には求められているのではないでしょうか。
参考記事
- https://weathernews.jp/news/202507/020146/
- https://coki.jp/article/column/54821/
- https://www.asahi.com/articles/ASQDH5QH9QDHUTIL01D.html

まとめ:備えあれば憂いなし
「トカラの法則」が話題になるたびに、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし、こうした“法則”が完全に科学的に立証されていない以上、それ自体に振り回される必要はありません。
むしろ大切なのは、どんな情報があっても冷静に自分と家族を守るための備えができているかを確認することです。
本章では、「備えあれば憂いなし」という言葉の本質を掘り下げながら、現実的な防災行動の視点を整理していきます。
“備える”とは、心の余裕を持つことでもある
災害が起きたとき、慌てず冷静に行動できるかどうかは、事前の準備にかかっているといっても過言ではありません。
非常食や水、ライトやラジオといった物理的な備えも重要ですが、それ以上に日頃から「どこに避難すべきか」「家族とはどの手段で連絡を取るか」といった意識の備えが重要です。
特にトカラ列島のように、地震が頻発する地域に住んでいる、あるいは旅行で訪れる人にとっては、“何かが起きたときに自分はどう動くか”をシミュレーションしておくことが命を守る力になります。
不安をあおる情報に飲み込まれるより、「自分にできることをやっておこう」という考え方が、最も理にかなった行動といえます。
不確かな“予兆”ではなく、確実な“備え”を信じよう
「トカラの法則」には過去に“当たった”とされる事例が複数存在しますが、それが因果関係であるかは依然として不明です。
実際には、トカラ列島はもともと地殻変動が活発なエリアであり、群発地震自体は定期的に起きる現象です。
そして、日本列島全体がプレートの接点に位置しているため、全国的にいつどこで地震が起きても不思議ではありません。
だからこそ、根拠のあいまいな“法則”に頼るよりも、平時からできる防災対策を一つひとつ積み上げていくことが重要なのです。
それが、最終的に「憂いなし」につながります。
家庭で今日からできる“備え”チェックリスト
| 対策項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 避難場所の確認 | 自宅周辺のハザードマップを確認し、最寄りの避難所を把握する |
| 家族との連絡手段 | 災害時に連絡を取る手段(SMS、伝言ダイヤルなど)を事前に共有 |
| 非常用持ち出し袋 | 水・食料・モバイルバッテリー・常備薬・マスクなど3日分を準備 |
| 家具の固定 | 寝室や出入口付近の家具の転倒防止を徹底 |
| 地域情報の受信 | 気象庁や自治体、防災アプリで最新情報をチェック |
| 地震保険の見直し | 住まいのリスクに応じた補償内容を確認・更新 |
このように、物理的な備えだけでなく、心構えや情報収集の習慣もまた“備え”の一部です。
「トカラの法則」が注目される今こそ、防災について家族と話し合う良いきっかけにしてみてくださいね。
“法則”に振り回されず、防災意識を育てる
「トカラで揺れたら次に本州が危ない」――こうした話が広まる背景には、多くの人が将来への不安を抱えていることが表れています。
情報があふれる現代では、“不安をあおるような断片的な噂”に流されてしまうこともあります。
しかし、事実として地震の予知は現在の科学では非常に困難です。
そのため、情報の真偽を自分で見極めること、そして「備える」ことだけは他人任せにしないという姿勢がますます大切になっています。
「トカラの法則」が当たるかどうかではなく、「備えができているか」を見直す視点を持っておくと、どんな状況にも対応しやすくなりますよ。
参考記事
- https://www.asahi.com/articles/ASQDP6RT3QDPULZU00J.html
- https://news.yahoo.co.jp/articles/0f40eac19cb219728df2e15a912a07a74a2216d4
- https://gendai.media/articles/-/100033
- https://weathernews.jp/s/topics/202106/040215/